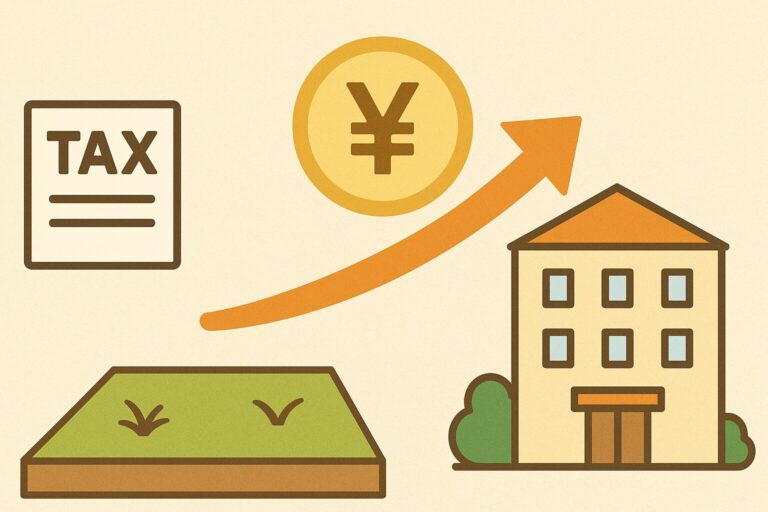遊休地を放置すると税負担が重くなる
相続や投資で取得した土地を長年利用せずに放置しているケースは少なくありません。しかし、土地は利用していなくても固定資産税や都市計画税といった税金がかかり続けます。さらに、将来的に相続が発生時の評価額も建物が存在する場合よりも割高になります。
つまり、遊休地は「使わなくても税金だけがかかる資産」と言えるのです。
活用によって評価額が下がるケース
不動産は「利用状況」によって税務上の評価額が変わります。たとえば、遊休地をそのまま所有しているよりも、アパートやマンションなど収益物件として活用している方が、相続税評価額が下がる場合があります。
-
貸家建付地評価
住宅やアパートを建てて第三者に貸すと、土地評価額に一定の減額補正(減額割合=借地権割合×借家権割合)が適用されます。 -
小規模宅地等の特例
一定の面積を限度として減額される特例で、賃貸事業以外の事業用の場合は最大80%、賃貸事業用の場合は最大50%まで評価額が減額されます。ただし、賃貸事業用の宅地が特例を受けるためには相続開始の3年以上前から賃貸事業の用に供されている必要があります。
これらの制度により、建物が建てられて活用されている土地(建付地)の方が将来的な相続税の負担を大幅に軽減できる傾向にあります。
活用方法と節税効果の具体例
-
駐車場経営
初期投資が比較的少なく、安定した収益を得やすい方法。固定資産税を収益で相殺でき、事業用資産として評価額が下がることもあります(小規模宅地等の特例のみ適用)。 -
アパートや貸家の建築
貸家建付地評価により、土地の相続税評価が減額。さらに家賃収入で税金負担を軽減可能。 -
事業用施設への転用
貸倉庫や事務所などにすると、相続税や固定資産税の特例が使える場合があります。 -
土地信託・等価交換
デベロッパーに土地を信託したり、建物との交換を行うことで、収益を確保しつつ税務上の評価を抑えられるケースもあります。
注意すべきポイント
-
節税を目的にしただけの無理な活用は、収支が合わず逆に負担になることがあります。
-
地域の需要、将来の資産承継計画を踏まえて活用方法を選択することが重要です。
-
税制は改正される可能性があるため、最新の情報を踏まえた専門家への相談が欠かせません。
まとめ
遊休地をそのままにしておくと、固定資産税や相続税の負担が大きくなります。逆に、賃貸や事業用に活用することで、税負担を減らしながら収益を生む資産に変えることが可能です。
遊休地をお持ちの方は、「節税」と「資産価値の最大化」を両立する活用方法を検討することをおすすめします。
当社では、不動産価値の専門家である不動産鑑定士が建築後の収支を徹底的に分析し、資産価値の最大化をサポートします。
まずは、下記お問い合わせフォームより気軽にお問い合わせください。