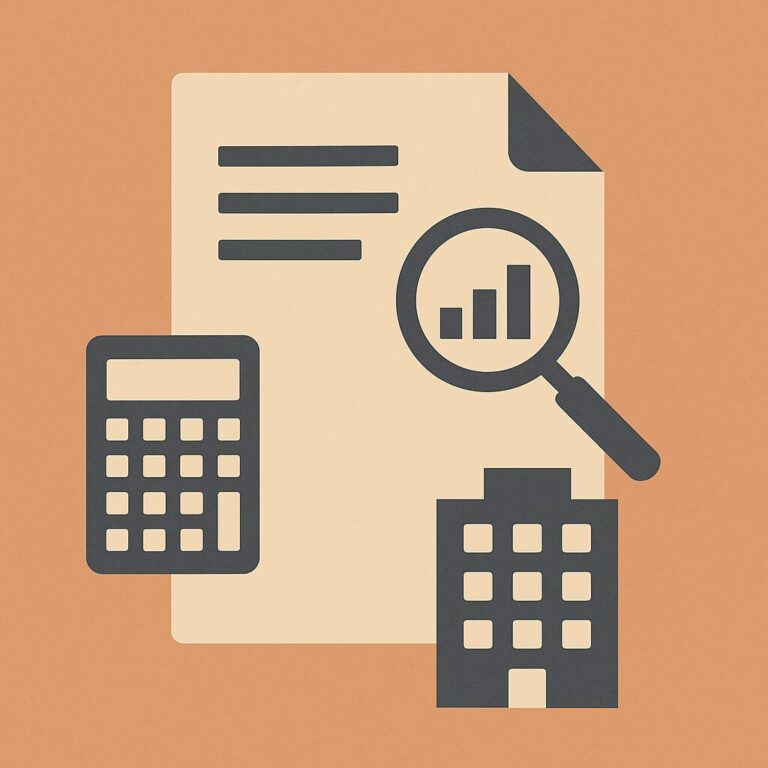継続賃料とは
継続賃料は賃料・地代の増減額請求といった現行の賃料を改定する際に算出される賃料であり、不動産鑑定評価基準では、継続賃料を 「不動産の賃貸借の継続に係る特定の当事者間において成立するであろう適正賃料」 と定義しています 。
つまり、新規契約時に想定される「正常賃料」とは異なり、既存の契約関係を前提に形成される点が特徴です。
価格時点と直近合意時点の違い
-
価格時点とは
価格時点は、価格を判定する基準となる日を指し、継続賃料の場合は賃料増減請求がなされる場合の「改定基準日」が価格時点となります。 -
直近合意時点
当事者間で前回の賃料改定が合意された時点を指します。自動更新で更新されている場合の更新日は合意がされていないため、直近合意時点にはなりません。
また、直近合意時点は当事者間で合意があった時点であることから、合意が実際にあったかどうかでいつを直近合意時点とするのか争点になる場合もあります。
継続賃料の評価では、直近合意時点から価格時点にかけての経済事情の変化、契約・改定の経緯、内容等を総合的に勘案するため、直近合意時点を適切に判断することが重要になります。
賃料形成に影響を与える要因
-
一般的要因:経済情勢、金融環境、税制、物価動向等
-
地域要因:土地・公租公課価格の推移、立地条件、交通利便性、商業集積度、地域の発展性等
-
個別的要因:周辺賃料の推移・改定の程度、契約の内容・経緯、建物の性能・老朽度、修繕履歴、テナント状況、契約条件(保証金・敷金等)等
これらを適切に分析することで、当事者双方が納得可能な「合理的水準」が導かれます。
継続賃料の評価手法
① 差額配分法
-
新規賃料と現行賃料の差額を算定し、貸主・借主の事情に応じて合理的に按分する方法。
-
裁判実務でも多用される中心的手法。
② 利回り法
-
対象不動産の価格時点の価格(基礎価格)に、直近合意時点における対象不動産の利回りに周辺類似不動産の利回り等を考慮して求められた期待利回りを乗じて賃料を算定する方法。
-
収益不動産に適用されるケースが多い。
③スライド法
-
直近合意時点から価格時点にかけての物価指数や地価指数等の経済指標の変動に基づき、直近合意時点の賃料を変動させる方法。
-
経済情勢(インフレ・デフレ等)の影響を反映させることに適している。
-
単独で用いることは少なく、差額配分法等と併用されることが多い。
-
裁判所実務では、経済指数を反映させる合理性が認められる一方で、指数変動が直ちに賃料変動に結びつかない点に注意が必要。
④ 賃貸事例比較法
-
周辺の類似物件の賃料改定事例を参考に評価。
-
契約条件や個別要因を調整して水準を求める。
- 賃料改定事例は開示されておらず、契約期間、経緯等も異なる等個別性が強いため類似する賃料改定事例を探すことは困難である場合が多く、適用されることは少ない。
これらの4手法(実務上は④を除く3手法のことが多い)で試算された賃料を契約・改定の経緯等を踏まえ、各事情を適切に反映されているかを吟味したうえで、各賃料に重みづけを行い鑑定評価額が決定されます。
まとめ
継続賃料とは、単に「相場の家賃」ではなく、
-
既存契約・改定の経緯、内容
-
市場環境の変化
-
当事者間の合理的利害調整
などを踏まえて算定される当事者間においてのみ成立する特殊な賃料です。
賃料・地代の改定でお悩みでしたら、まずは下記お問い合わせフォームより気軽にご連絡ください。